先日、モードダイヤルのロック機構についての記事で現行の一眼レフとミラーレスカメラが全部で70機種と書いたが、その後実売価格をチェックしなおしたところ4機種減って66機種になっていた。
一応書いておくと、ワタシが調査対象にしているのはヨドバシ.comの表示価格で、ワタシ内規定ではヨドバシ.comで、
- 「在庫あり」表示=現行
- 「販売を終了しました」表示=非現行
というふうに分類している。
ただし、ヨドバシ.comで販売終了であってもビックカメラには在庫がある場合もあるし、Amazonだとか楽天市場だとかを探すと出てくるケースも多々ある。なので、あくまでワタシ内規定ということである。
と言うのはさておき、年末ともあって、相場はややアレ気味、違った、荒れ気味な印象となっている。買う機会をねらっている人にはわりとおいしい状況であるかもしれない。
そういうのとはまったく関係なしに、ふと、
「これ全部買ったらいくらするんだろ?」
と思ったのである。
まあ、データは表計算ソフトでまとめているのでちょいちょいっと数式を入れてやれば数字は出てくる。合計なら「SUM」、平均値が知りたければ「AVERAGE」、数量を見たいなら「COUNTA」とかいろいろだ。
これがけっこうはまる。
ものすごーく無意味な計算なのだが、やっているうちにやたらと楽しくなるときがあるのだ。
その楽しさを分かち合えたらなぁ、というのもあって、記事にしてみることにした。
正直、かなりのおばかネタではあるが、年末年始の本気で暇をつぶしたくなったときにでもご笑覧いただければと思う。
かなぁり長いので忙しいときには絶対にご覧にならないように注意だけしておく。
目次
機種数は一眼レフ26 vs ミラーレスカメラ40
冒頭からおばかな数字を出すのも気が引けるので、多少まじめっぽいところから紹介する。
フルサイズ以下のレンズ交換式カメラを発売している大手メーカーは国内に8社あり、そのうち、一眼レフを発売しているのは4社にすぎない。
と言っても、ソニーの2機種は一眼レフっぽくはあっても一眼レフではない。が、ミラーレスカメラに分類するのもちょっと違う気がするので一眼レフに混ぜているだけで、それを差し引けば一眼レフのメーカーは3社で機種数は24。ミラーレスカメラは7社で機種数は40となる。
■メーカーごとの機種数
| 一眼レフ | ミラーレス | 小計 | |
|---|---|---|---|
| オリンパス | 0機種 | 5機種 | 5機種 |
| キヤノン | 11機種 | 5機種 | 16機種 |
| シグマ | 0機種 | 2機種 | 2機種 |
| ソニー | 2機種 | 12機種 | 14機種 |
| ニコン | 10機種 | 2機種 | 12機種 |
| パナソニック | 0機種 | 6機種 | 6機種 |
| フジフイルム | 0機種 | 8機種 | 8機種 |
| ペンタックス | 3機種 | 0機種 | 3機種 |
| 合計 | 26機種 | 40機種 | 66機種 |
機種数のトップはキヤノンの16。次いでソニーが14。ニコンの12がつづく。
4位以下はフジフイルムが8、パナソニックの6、オリンパスが5、ペンタックスの3、シグマの2となる。
こんなふうに数字にしてしまうと、ほんとに「3強」時代が来ちゃってるんだなぁと思う。
2016年はカメラの当たり年だった
これもなにげにおもしろかったので載せてみる。
■発売年ごとの機種数
| 発売年 | 機種数 |
|---|---|
| 2013年 | 2機種 |
| 2014年 | 7機種 |
| 2015年 | 6機種 |
| 2016年 | 19機種 |
| 2017年 | 15機種 |
| 2018年 | 17機種 |
あくまで現行機種の範囲での発売年であって、その年に発売された機種数ではない。
これを見ると、最近のカメラの寿命の短さがよくわかる。ぶっちゃけ、発売から3年も経つともう古株あつかいしてOKな感じである。
ちなみにいちばん古いのは2013年11月15日発売のソニーα7である。次がその半月ほどあとの11月28日にニコンDfが発売されている。
興味深いのは2016年で、年明け早々にニコンがD5とD500を発表したのを皮切りに、オリンパスPEN-FやフジフイルムX-Pro2、キヤノンEOS-1D X Mark IIとEOS 5D Mark IV、ソニーα99 IIといった大物が出て、さらにシグマのsd Quattroとsd Quattro Hが登場。ラストをオリンパスがE-M1 Mark IIで締めくくった。とまあ、近年まれに見るカメラの当たり年だったのである。
月ごとの数字もおもしろい。
■発売月ごとの機種数
| 発売月 | 機種数 |
|---|---|
| 1月 | 2機種 |
| 2月 | 6機種 |
| 3月 | 12機種 |
| 4月 | 6機種 |
| 5月 | 2機種 |
| 6月 | 6機種 |
| 7月 | 3機種 |
| 8月 | 2機種 |
| 9月 | 11機種 |
| 10月 | 5機種 |
| 11月 | 7機種 |
| 12月 | 4機種 |
商売をしている人にはあたりまえすぎるかもしれないが、これだけ露骨に3月と9月に偏っているのは小気味よいぐらいである。
各社とも売れる時期を考えて製品開発をやっていることがうかがえる。
1千万円あれば現行全機種が買える(かも)
つづいて、ボディ単体の実売価格を見ていく。
キット販売しかしていないパナソニックDC-GF10/90はボディ単体の価格が不明なことになるのでここではカウントしていない。
なお、数字はヨドバシ.comの表示価格(税込み)で、ポイント還元の分はふくめていない。また、チェックしたのは2018年12月26日の午後であり、この時点を「執筆時」として掲載する。
で、現行65機種の合計価格は執筆時で、
11,656,000円
となった。
ちなみに、発売時の数字を合計すると、
14,601,710円
である。
おおざっぱには300万円ばかり値崩れしていることになる。お買い得と言えばお買い得なんではないかと思う。
たぶん店頭で値切れば1千万円を切るかもしれない。どなたかチャレンジしてみたら結果を教えてほしい。
せっかくなのでもうちょっと細かく見てみる。
■実売価格の合計と平均
| ミラーレス | 一眼レフ | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,087,210円 | 5,568,790円 | 11,656,000円 |
| 平均 | 156,082円 | 214,184円 | 179,323円 |
機種数ではミラーレスカメラが多数派なのに、合計価格はかなり接近している。それだけミラーレスカメラに安価なものが多いというわけで、平均価格は58,102円も違っている。
なお、レンズキットやダブルズームキットなどもふくめると総額は、
25,005,000円
ほどとなる。
ただし、このへんのデータはわりと雑に集めているだけなので、それなりに誤差もあると思う。ご注意いただきたい。あと、念のために書いておくが、こちらの数字にはDC-GF10/90もふくめている。
蛇足だが、現行機種での最高価格と最低価格のそれぞれトップ3もあげておく。
■お高いカメラ3選
| 機種名 | 税込み実売価格 |
|---|---|
| ニコンD5(XQD仕様) | 606,250円 |
| ニコンD5(CF仕様) | 606,160円 |
| キヤノンEOS-1D X Mark II | 598,690円 |
■お安いカメラ3選
| 機種名 | 税込み実売価格 |
|---|---|
| フジフイルムX-A5 | 41,250円 |
| ソニーα5100 | 46,170円 |
| キヤノンEOS Kiss X90 | 46,440円 |
D5の1台分の予算でX-A5なら14台買えて28,750円もお釣りがもらえるのである。なんだかすごい話である。
有効画素数を合計すると16億8518万画素
撮像センサーに関連する数字も見てみよう。まずは有効画素数だ。最小値はパナソニックDC-GH5Sの1028万画素、最大値はキヤノンEOS 5Ds/5DsRの5060万画素となる。
■メーカー別有効画素数の合計と平均
| 合計 | 平均 | |
|---|---|---|
| オリンパス | 8882万画素 | 1776万画素 |
| キヤノン | 4億4610万画素 | 2788万画素 |
| シグマ | 6810万画素 | 3405万画素 |
| ソニー | 3億6990万画素 | 2642万画素 |
| ニコン | 3億2798万画素 | 2733万画素 |
| パナソニック | 1億0324万画素 | 1721万画素 |
| フジフイルム | 1億9608万画素 | 2451万画素 |
| ペンタックス | 8496万画素 | 2832万画素 |
ここでもやはり「3強」の構図は揺るぎなく、業界いちばんの画素持ちはキヤノン。次いでソニー、ニコンの順となった。
一方、1機種あたりの画素数では意外にもシグマが平均3405万画素でトップを奪取。これは3層構造のFoveonセンサーならではの数字である点に注意すべきである(CIPA基準だと3層の画素数の合計になるので、Quattroの有効画素数は記録画素数の約1.5倍になる)。
オリンパスとパナソニックの平均値が1700万画素台なのはセンサーサイズの小さなマイクロフォーサーズだからだ。
有効画素数を全部合計すると16億8518万画素で、これは中国の人口(2017年で13億8600万人だった)よりも多い。
また、平均値は2553万画素であり、2400万画素が現行機種の標準的スペックと考えていい。
ちなみに、1画素あたりのサイズは平均で4.5μm程度。全部足しても294.7μm。だいたい0.3mmほどにしかならない。
0.3mmなら肉眼でも見えると思うかもしれないが、1画素の幅は大きいもので6.5μmなのだからまず見えないと思ったほうがいいだろう。
各機種の最高ISO感度の合計は12,857,600。10進数ではないのでこの数字にはあまり意味はないが、この半分強をニコンD5とD500、D7500の3機種だけでたたきだしているのは驚嘆に値する。だからなんなの?とか聞かれたら困るけれど。
公称のファイルサイズは数字を探すのが面倒くさいものもあったりするので、わかっている48機種のぶんだけ紹介する。
■ファイルサイズの合計と平均
| 合計 | 平均 | |
|---|---|---|
| RAW | 1,713MB | 35.7MB |
| JPEG | 671MB | 14.0MB |
なお、RAWについては14bitが選べるものは14bitの、ロスレス圧縮または圧縮RAWの数字をもとにした。また、JPEGはフル画素(ラージサイズ)の最高画質となるモードでの数字をもとにした。
一眼レフは1,350点測距で平均7コマ/秒
測距点数はミラーレスカメラを入れるかどうかで悩んだが、なにせ、公称値とカメラで選択可能な測距点の数が違ったりするし、任意選択時のフレームの位置というだけだとものすごい数字になるものもあったりする。と言うのもあって、ここでは一眼レフだけに絞ることにした。
なお、ニコンD5とD500の測距点数については、ここでは公称値どおりの153点(うちクロス測距点は99点)としているが、任意に選択可能な測距点の数では55点(クロス測距点は35点)しかない。
■一眼レフの測距点数
| 合計 | 平均 | |
|---|---|---|
| 測距点数 | 1,350点 | 51.9点 |
| クロス測距点数 | 798点 | 30.7点 |
案外に平均点数が多い(テストじゃないんで「高い」ではないところに注意)のは、エントリークラスの測距点数が増えたことと、一眼レフ自体が減っているからだ。
現状、高級機は一眼レフに多く、傾向として測距点も多めだからというのが理由と考えられる。
その影響もあって、クロス測距点の率は全体の59.1%と高い数字となった。ローエンド機だと9.1%(11点中1点がクロス)、11.1%(9点中1点がクロス)というものもある一方、全点がクロス測距点のものも少なくない。
■クロス測距点率が100%のカメラ
| EOS 6D Mark II | 45点 |
| EOS 7D Mark II | 65点 |
| EOS 80D | 45点 |
| EOS 9000D | 45点 |
| EOS Kiss X9i | 45点 |
■クロス測距点率が低いカメラ
| EOS Kiss X9 | 11.1% | 9点中1点 |
| EOS Kiss X90 | 11.1% | 9点中1点 |
| D3500 | 9.1% | 11点中1点 |
| D3400 | 9.1% | 11点中1点 |
ほんとは測距点のカバーエリアの広さとかを数字で比べられるとおもしろいのだが、どのメーカーも成績のいいものしか数字を書かない習性があるため調べきれないのが現状である。こういうところももう少し改善されるべきなんではないかと思う。
一方、連写スピードは機種による差がとても大きいうえに条件つきでの最高速(露出が固定になるとか絞り値の設定範囲がかぎられるとか)のも混じっていたりするのでちょっとあやふやな数字になってしまうが、まあ与太記事なんだし、広い心でお許しいただければと思う。
連写スピードのトップ5は、と思ったら4位タイのが5機種もあったりする。
■連写速度が速いカメラ
| ソニーα9 | 20コマ/秒 |
| パナソニックDC-G9 | 20コマ/秒 |
| フジフイルムX-T3 | 20コマ/秒 |
| オリンパスE-M1 Mark II | 18コマ/秒 |
| キヤノンEOS-1D X Mark II | 14コマ/秒 |
| フジフイルムX-H1 | 14コマ/秒 |
| フジフイルムX-T2 | 14コマ/秒 |
| フジフイルムX-T20 | 14コマ/秒 |
| フジフイルムX-E3 | 14コマ/秒 |
X-T3は1.25倍クロップで30コマ/秒、DC-G9とDC-GH5は6Kフォトモードで30コマ/秒連写も可能だが、原則としてフル画素かつAF追従で出せる最高速の数字で計算している。
上位はことごとくミラーレスカメラで、いずれも電子シャッター使用時の数字だ。
一眼レフの最高速は4位タイに食い込んだEOS-1D X Mark II。その次がニコンD5の12コマ/秒だ。さすがはハイエンドと見るべきか、こんなにコストをかけてもこの程度なのが一眼レフの限界と受け取るべきかはむずかしいところだ。
なお、平均の連写スピードを見るとこんな感じである。
■平均連写スピード
| ミラーレス | 9.4コマ/秒 |
| 一眼レフ | 7.0コマ/秒 |
| 全体 | 8.4コマ/秒 |
ミラーを動かさなくていいミラーレスカメラのほうが、連写スピードは上げやすい傾向があるのがよくわかる。
ただし、動く被写体への追従性は、それこそくそ低いものも少なくないので、AF+連写のテストをやるとまだまだ一眼レフのほうが歩留まりはいい。ようは、スペックに引きずられてはいけないということである。
次はシャッターの最高速を見てみよう。
いわゆるメカシャッター(物理的な先幕と後幕によって露光時間を調節するもの。先幕のみを電子シャッターに置き換えた電子先幕シャッターもふくむ)の場合は、
■シャッター最高速別の機種数
| 1/8000秒 | 35機種 |
| 1/6000秒 | 2機種 |
| 1/4000秒 | 28機種 |
ちなみに、1/6000秒のユニットを搭載しているのは、ペンタックスのKPとK-70である。こういうところにもオリジナリティーがあらわれる。
電子シャッターでメカシャッターよりも高速シャッターが切れるものは21機種あって(メカでも電子でも最高速が同じα9とかはふくまない)、うちわけは、
■電子シャッターの最高速別の機種数
| 1/32000秒 | 11機種 |
| 1/24000秒 | 1機種 |
| 1/16000秒 | 9機種 |
明るいレンズを昼間でも開けて撮りたいならこのあたりの機種を選ぶのがいい。ただし、ローリング歪みは発生するので、動きの少ないものをねらう場合にかぎると考えたほうがいい。
電気を食うミラーレスのほうが小容量だった
標準装備のバッテリーについての数字を見てみる。わざわざそう書いたのは、ニコンD850やD500のように、縦位置グリップ(ニコンだと「マルチパワーバッテリーパック」という名称だが)装着時に別のタイプのバッテリーが使える機種もあるからだ。
で、現行機種の標準バッテリーのうちの容量が最少のものはパナソニックDC-GF10/90に付属のDMW-BLH7で、容量は980mAhしかない。撮影可能枚数はこれで210枚。容量1,000mAhあたりで考えると309枚となる。実はこれ、ミラーレスカメラとしてはわりといい数字だったりする。
一方、最大容量はキヤノンEOS-1D X Mark IIのLP-E19で2,700mAhもある。たっぷり容量なので撮影可能枚数も多く、公称値は1,210枚となっている。容量1,000mAhあたりだと448枚。DC-GF10/90の1.5倍程度のライフがある。
全体の数字を見てみると、以下の表のようになる。
■バッテリー容量と撮影可能枚数
| 一眼レフ | ミラーレス | 全体 | |
|---|---|---|---|
| 合計容量 | 41,450mAh | 54,380mAh | 95,830mAh |
| 平均容量 | 1,594.2mAh | 1,359.5mAh | 1,452.0mAh |
| 撮影可能枚数 | 26,230枚 | 13,762枚 | 39,805枚 |
| 平均枚数 | 1,009枚 | 344枚 | 612枚 |
| 1,000mAhあたり | 633枚 | 253枚 | 415枚 |
機種数はミラーレスカメラのほうが多いので、合計のバッテリー容量はミラーレスカメラが上だが、平均のバッテリー容量で見ると一眼レフのほうが大きい。
これはつまり、一眼レフよりも消費電力が大きいはずのミラーレスカメラに対して、メーカー各社が容量の小さなバッテリーしか用意していないことを意味しており、このことが「ミラーレスカメラは電池が持たない」という風説を助長している可能性がある。
まあ、ボディの小型化のため、と考えるのが自然だし一般的だとは思うが。
その結果、標準バッテリー1個で一眼レフは1,009枚も撮れるのに対して、ミラーレスカメラは344枚と少ない。電池を食う特性を持っているのに、さらにバッテリー容量まで削られているのだからたまったものではないのである。
注目するべきは容量1,000mAhあたりの撮影可能枚数で、言うなればカメラの燃費がわかる数字だ。この数字が一眼レフは平均で600枚を超えているのに対して、ミラーレスカメラは平均250枚程度。2倍以上の開きがある。
なお、総充電時間は調べる手間を考えるだけで気が遠くなったため省略している。なんだよ、って思った方は、ご自身で各社のウェブサイト、使用説明書PDFをくまなくあたって数字をお知らせいただけると幸いである。
ところで、カメラの燃費を機種ごとに見ていくと事情はまた少し違ってくる。
まずワーストは順当と言えば順当にシグマsd Quattro Hとなった。容量1,860mAhのバッテリーで187枚しか撮れない。ちなみにこの数字は、使用説明書PDFの163ページに記述があるのでご確認いただきたい。容量あたり101枚である。
APS-Cサイズのsd Quattroはもう少しマシで、同じバッテリーで235枚(同じく159ページを参照のこと)撮れるから、容量あたり126枚となる。
これはFoveonという撮像センサーの電池の食いっぷりがすごいのであって、シグマ好きのワタシとしては将来がとても心配なのである。
というのは、APS-Hサイズで容量あたり100枚とかだとフルサイズFoveonは容量あたり60枚ぐらいになりかねない。バッテリー1個で111枚とかだぞ。ヤバいでしょ。ヤバいですよ社長。
気を取り直して。っと。
一方、燃費のいいほうはニコンD5の容量あたり1,890枚(2,000mAhで3,780枚撮れる)という成績。素晴らしい。節電を心がけたい方はD5を買うべきである。製造時の消費電力に目をつぶることができるならだけれど。
ちなみに、燃費のいい順に並べると上位はずらっと一眼レフが占める。ミラーレスカメラは19位のソニーα5100(容量あたり392枚)がトップというていたらくである。
が、念のために書いておくと、一眼レフであってもミラーレスカメラより燃費の悪いヤツもいる。キヤノンのEOS 5Ds/5DsRは容量あたり375枚、同じくキヤノンEOS 7D Mark IIは容量あたり359枚しか撮れない。α5100よりも電池食らいなのである。
つまり、おおざっぱな傾向としては一眼レフのほうがミラーレスカメラよりも燃費はいいが、それはあくまで傾向にすぎないのだ、ということである。機種による差もあるのだから、思い込みや印象で判断するのは避けてもらいたい。
ついでに書くと、ちまたでけっこう電池が持つと評判のニコンZ7、Z6は容量あたり173枚と163枚という数字。キヤノンEOS Rは198枚でニコンの2機種を少し上まわる。
さらについでの話になるが、ミラーレスカメラでは屈指の電池の持ちのよさを誇るソニーα9、α7R III、α7 IIIだが、これはバッテリーの容量が増えただけなので、誉めすぎないほうがいいと思う。
容量あたりの撮影可能枚数を見ると、
■最新「α」3機種の燃費
| α9 | 211枚 |
| α7R III | 232枚 |
| α7 III | 268枚 |
でしかない。
その前の世代の3機種の数字と見比べてほしい。
■ひとつ前「α」3機種の燃費
| α7R II | 284枚 |
| α7S II | 304枚 |
| α7 II | 265枚 |
α7 IIとα7 IIIは誤差の範囲レベルだが、α7R IIとα7R IIIを比べれば、明らかに「II」世代のほうが燃費がいいのである。
まあ、スペック上の話にすぎないので、実際のところ、たいした意味はないのだけれど。
即金で買ったとしてお持ち帰りは可能?
ボディの大きさや重さは、最大値と最小値を比べるのがとても楽しい。まずは幅から。
■ボディの幅
| パナソニックDC-GF10/GF90 | 幅106.5mm |
| ニコンD5 | 幅160.0mm |
いちばん大きなD5といちばん小さなDC-GF10/90とでだいたい1.5倍違う。D5を2台並べたのとDC-GF10/90を3台並べたのがほぼ同じなわけだ。
■ボディの高さ
| ソニーα5100 | 高さ62.8mm |
| キヤノンEOS-1D X Mark II | 高さ167.6mm |
同じカメラなのに2台のあいだに10cm以上の開きがある。α5100の上にα9を重ねても158.4mmだから、まだEOS-1D X Mark IIのほうが高い。
■ボディの奥行き
| パナソニックDC-GF10/90 | 奥行き33.3mm |
| ニコンD5 | 奥行き92.0mm |
58.7mm差というのはなかなかにインパクトのある数字である。が、実はパナソニックDC-G9の奥行きが91.6mmあることも知ってもらいたい(D5と0.4mm差である)。こういう発見があるのも数字遊びのおもしろいところである。
次は重さ。ここは一眼レフの独壇場で、上位4機種はバッテリーとメモリーカードをふくめた状態で1kgを超える。
■重いカメラ4選
| キヤノンEOS-1D X Mark II | 1,530g |
| ニコンD5 | 1,405g |
| ペンタックスK-1 Mark II | 1,010g |
| ニコンD850 | 1,005g |
ちなみに、ミラーレスカメラの最重量はパナソニックDC-GH5の725g。撮像センサーの小さなマイクロフォーサーズなのに、と笑う人もいるが、画像処理関係の回路や液晶モニター、EVF、バッテリーなどが小さくできるわけでもなんでもないし、使う人間の手が小さくなったのでもないし、小型軽量さが重視されるクラスのカメラでもない。
放熱対策をきちんとやって、4K動画をまじめにノンストップ録画できるようにした結果でもある。そう考えれば、笑う人がおかしいことは自明である。
一方、軽いほうはミラーレスカメラの見せ場である。
■軽いカメラ3選
| パナソニックDC-GF10/GF90 | 270g |
| ソニーα5100 | 283g |
| キヤノンEOS M100 | 302g |
一眼レフの最軽量はニコンD5300の415gで、それでもDC-GF10/90の1.5倍強の重さがある。やはり一眼レフは重いのである。
もうちょっとおばかっぽい数字もあげておく。
■カメラのサイズと重さの合計
| 66機種の合計 | |
|---|---|
| 幅 | 8,678.5mm |
| 高さ | 6,308.5mm |
| 奥行き | 4,351.3mm |
| 質量(電・カ込) | 39,626g |
| 質量(ボディのみ) | 36,650g |
現行機種66台を横に並べると約8.68m。これは走り幅跳びの世界記録(8.95m)に27cm足りない。66機種の平均値は131.5mmなので、あと2機種増えれば並ぶ。パナソニックのS1とS1Rが出れば(そして、ほかの機種が消えなければ)ばっちりだ。
この数字は六畳間の長辺(江戸間だと3.52mである)の2.5倍ほど。横に並べて2列と半分ほどになる。さぞかし壮観であるに違いない。
背の高さを66台分足すと約6.31m。棒高跳びの世界記録が6.14mだから、最上段の2台ぐらいにぶつかることになる。
奥行きはアイカップをはずせるものははずした数字を記載して構わないルールになっているほか、突起物を省いても可なので、メーカーによってはグリップ背面側のでっぱっている部分をスルーしているケースがあるので要注意だ。
実際、ソニーα7 IIなどのスペック表には「59.7mm」という数字に「グリップからモニターまで」という注釈が添えられている。それがα7 IIIでは背面側の突起部もふくめたと思われる「73.7mm」と、「グリップからモニターまで」という注釈つきの「62.7mm」の2つの数字が記載されている。
細かい話はさておき、奥行きの合計は4.35mほどで、これは六畳間(江戸間)の対角線長(4.4mほど)とほぼ同じだ。なお、走り高跳びの世界記録は2.45mである。かすってもいない数字で申し訳ないが。
質量、つまり重さは、バッテリーとメモリーカードをふくめた状態で39.6kg。ある程度体力のある人なら持ち帰りは不可能ではない。と思うかもしれないが、むしろ重要なのは化粧箱の大きさである。
発掘しやすい場所にあったソニーα7R IIIの箱は幅24×高さ14×奥行き15.5cmほどだったから、66機種ともが同じサイズだと仮定しての総体積は343,728立方cmになる。
幅39×高さ19×奥行き10cmのコンクリートブロックに換算すると、だいたい46個分に相当する。つまり、幅195×高さ171×厚さ10cmの壁がつくれる量というわけだ。もしくは、幅50×奥行き39×高さ171cmの柱である。
ただし、これは凹凸をまったく考えずにならした場合の話で、実際には大小さまざまな化粧箱が混ざることとなるのを考えねばならないから、やはり持ち帰りは無理があると言わざるをえない。
が、ヨドバシ.comで注文するのであれば、送料は無料である。安心して注文していただきたい。
まとめ
さて、愚にもつかないばか話を延々書き連ねたら1万字を超えてしまってさすがにくたびれた。
が、この記事がそれなりにウケたらレンズ編も書こうかと思っている。体力的にしんどい気もするが。
いずれにしても、長ったらしいのを最後まで見捨てずに読んでくださったことに感謝したい。
↓いっしょに読むとさらに暇つぶしになります。
[kanrenc id=”1493″ target=”_blank”]
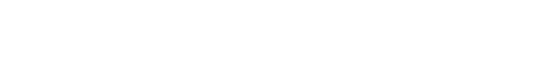




>正直、かなりのおばかネタではあ
りません。力作です。
レンズ編・・。期待して待っております。
ありがとうございますm(_ _)m
電池容量をmAhの数値で比較するのは誤り。電圧を考慮しなくては意味がない。電流x電圧、すなわちwhが電池の容量となる。デジカメ用の電池の電圧はすべて同じだと言うわけではないよ。